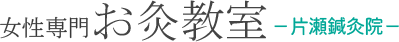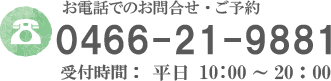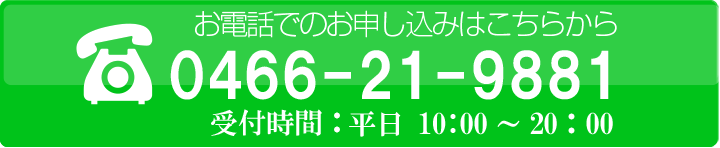コラム
お灸の歴史
2019年02月27日
お灸教室では紹介できないお灸のお話しを紹介します。
お灸教室に参加する前や参加した後にお読みください。
前回は、東洋医学の歴史についてお話ししましたが、今回は日本のお灸の歴史についてお話しします。
〈松尾芭蕉もしていたお灸〉
お灸は中国から伝来しましたが、その後日本独自の発展を遂げています。平安時代になると、お灸の原料のもぐさは「国産」が作られるようになった様です。
お灸が伝来した当時は、宮廷内や貴族が行っていたお灸療法ですが、鎌倉時代には武士に、さらに江戸時代では庶民にも広まり最盛期を迎えました。
俳人で有名な松尾芭蕉は、「股引の破れをつづり、笠の緒付けかへて、三里に灸すゆるより松島の月まづ心にかかりて」と、奥の細道の序文に書いています。

奥の細道は、東北から北陸にかけて旅をした紀行文ですが、「足三里というツボにお灸をしてすぐに」とあるように、旅立つ前に足三里というツボにお灸をしたとあります。
足三里というツボは、膝の下にあるツボで足の疲れをとる作用だけでなく、胃の調子や、体の疲れをとるツボとして有名です。(写真:足三里のお灸)

江戸時代に最盛期を迎え、民間で広く用いられたお灸療法は、昭和に入ってからも家庭で民間療法として行われていました。
「おじいちゃんやおばあちゃん、お父さんやお母さんが自宅でしていた。」という方もいらっしゃると思います。
その頃のお灸は、直接灸(透熱灸:とうねつきゅう、知熱灸:ちねつきゅう)と言って、モグサを直接肌の上に乗せて行っていました。やけどを作って免疫力を上げるという方法ですが、熱さを我慢したり、お灸の跡が残ることがありました。
お灸が熱いとか、やけどのイメージがあるのは、そのような方法が印象に残っているためだと思います。
〈現代のお灸〉
最近は、直接肌に乗せるお灸より、間接灸と言って台座が付いているものが主流になっています。温かさを感じる程度のお灸や香りがついたお灸など、初心者でも扱いやすいお灸が普及しています。
お灸の種類も豊富です。
☑温度が低いお灸・・・初心者におススメ
☑温度が高いお灸・・・上級者
☑アロマ灸・・・香りも楽しめます
(間接灸の種類) 詳細は、当ホームページの「お灸のススメ」をご覧ください。

写真左から
☑台座灸☑隔物灸(しょうがの上にもぐさが乗っている)☑棒灸
お灸教室の時間と料金について
※気軽にできる1回(50分)完結型のお灸教室です。
1.お好きな曜日とコースをお選びください
2.各コース2,500円です
| 開催日 | 開催時間 | 内容 | 料金 (税込み) |
| 月曜日 | 10:00~10:50 | 肩こりコース | 2,500円 |
|---|---|---|---|
| 11:30~12:20 | 腰痛コース | 2,500円 | |
| 13:00~13:50 | 冷え性コース | 2,500円 | |
| 14:30~15:20 | 不妊コース | 2,500円 | |
| 16:00~16:50 | 更年期障害コース | 2,500円 | |
| 水曜日 | 10:00~10:50 | 肩こりコース | 2,500円 |
| 11:30~12:20 | 腰痛コース | 2,500円 | |
| 13:00~13:50 | 冷え性コース | 2,500円 | |
| 14:30~15:20 | 不妊コース | 2,500円 | |
| 16:00~16:50 | 更年期障害コース | 2,500円 |
※駐車場はありません。
※お灸教室の人数は各6名~8名
アクセス
駐車場はありません
| 名称 | 片瀬鍼灸院 お灸教室 |
|---|---|
| 住所 | 〒251-0032 神奈川県藤沢市片瀬1-6-36 江ノ電柳小路駅から徒歩7分 駐車場はありません。 公共交通機関をご利用ください。 |
| 電話番号 | 0466-21-9881 |
| お灸教室開催日 | 月曜日・水曜日/10:00 ~ 17:30 |

女性専門片瀬鍼灸院All Rights Reserved.